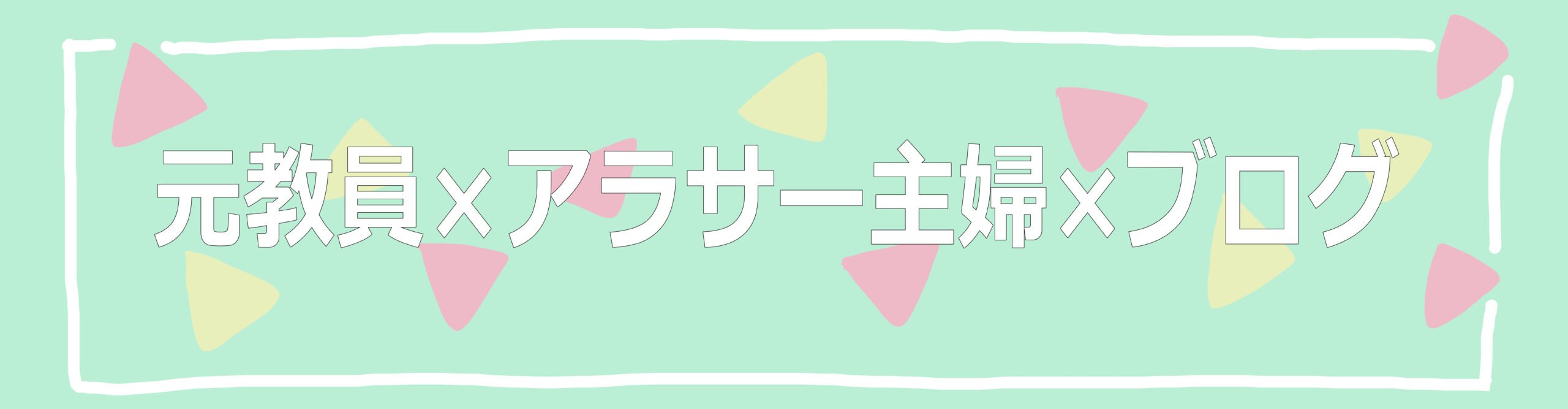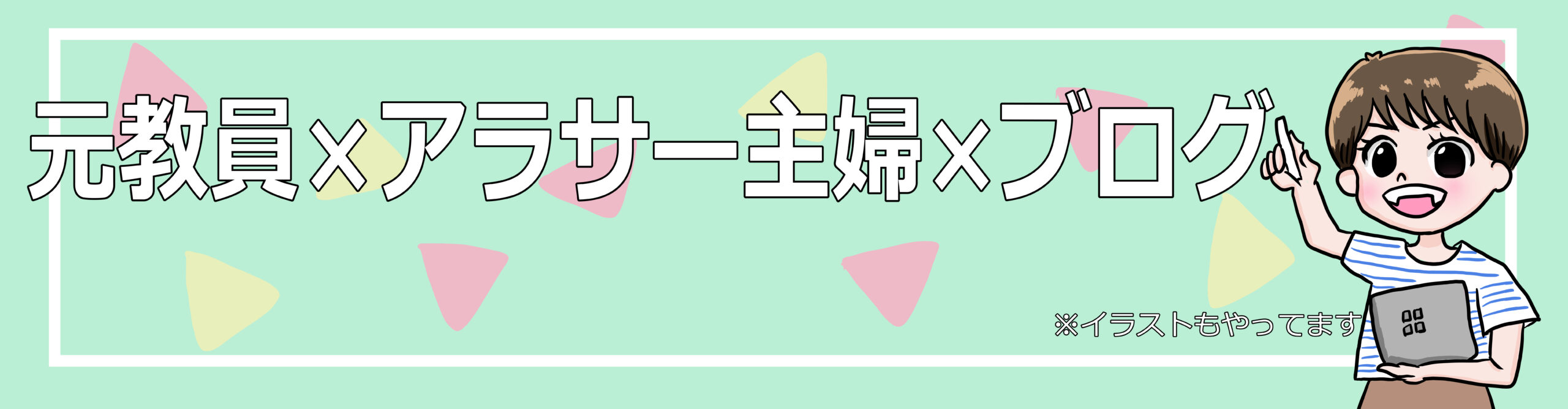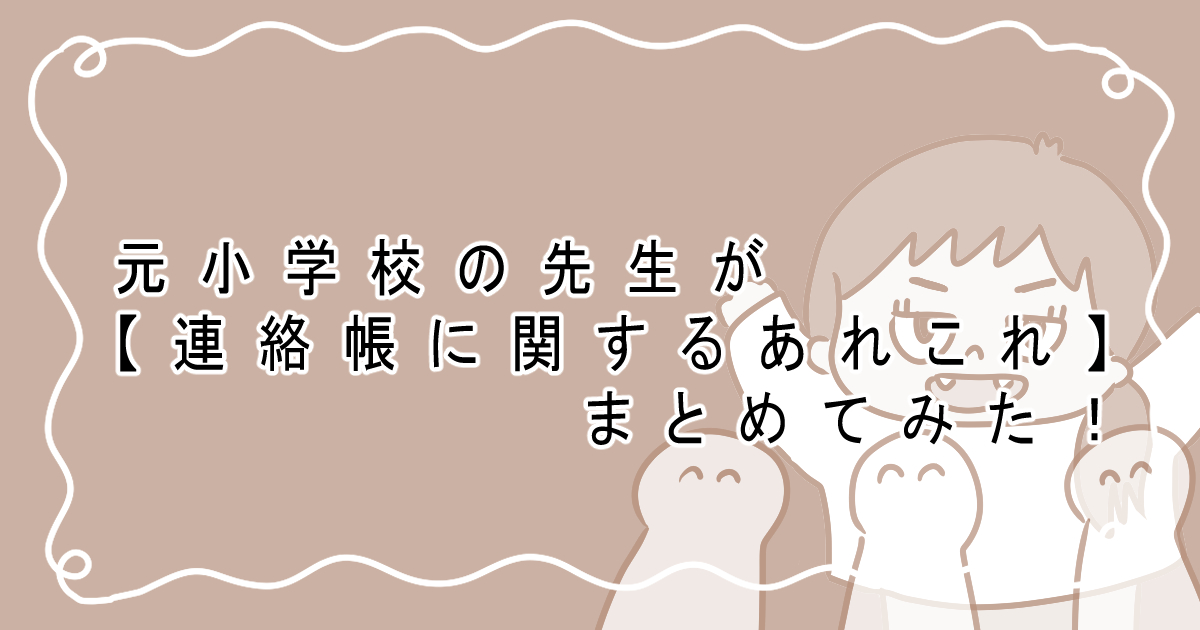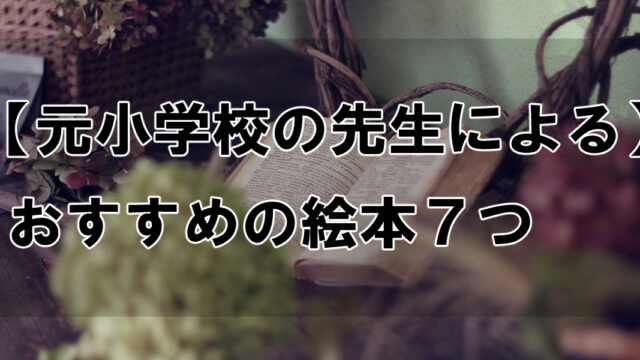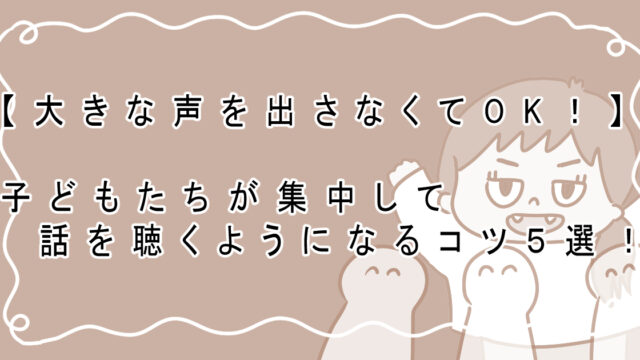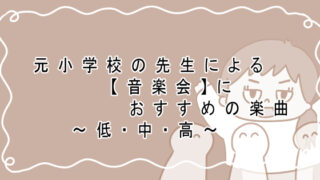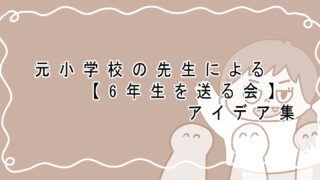こんにちは。元小学校の先生のまこちです。
過ごしやすい季節になってまいりましたね~~。
新任の方も学校生活にそろそろ慣れてきたころではないでしょうか。
今回のテーマは先生と保護者をつなぐ連絡帳!!

学校や先生によって対応が違うのではないでしょうか。
忙しい教師の学校生活ですが、連絡帳を有効に活用することで保護者の方とよりよい関係を気づくことができると考えています。
今回は、連絡帳のあれこれについてブログにまとめていきたいと思います。
・初任者の方
・教師の知識を増やしたい方
・教師の裏側を知りたい方
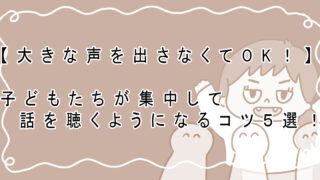

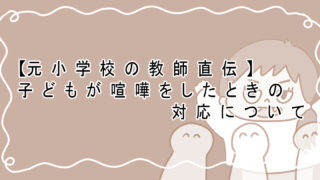
目次
私が考える連絡帳のあり方
【子どもたちにとってのルーティン】

私は「朝の準備の中で〇時までに提出する」というルールを子どもたちに話していました。
せわしなく朝の準備をする中でうるさくなるのは先生も子どももイライラします。
座って「書く」という動作をすることで落ち着くことができます。
毎日続けることでルーティーン化して落ち着いて学校生活に臨んでほしいものです。
【子どもたちが自分で予定管理】
連絡帳には、
- 時間割り
- 宿題
- 持ち物
- 連絡
などを記入します。
私の場合は、週予定を配布していたので、ほぼ宿題の内容しか書かせていませんでした。
子どもたちにも「週予定を見て持ち物とか必要な教科の準備をしてください。忘れるかも…と心配な子は自分で書きましょう。」
とその辺はお任せでした。
子どもたちは賢いもんで、自分で係や委員会などで各々必要なものを書いて管理している子もいました。
すぐ褒めてみんなに真似してもらいまいた。(笑)
お家の人にやってもらうのではなく、自分で予定管理をする力をつけるための意識付けのようなものではないかなと思います。
【先生と保護者との共通理解を図り信頼関係を深めるもの】
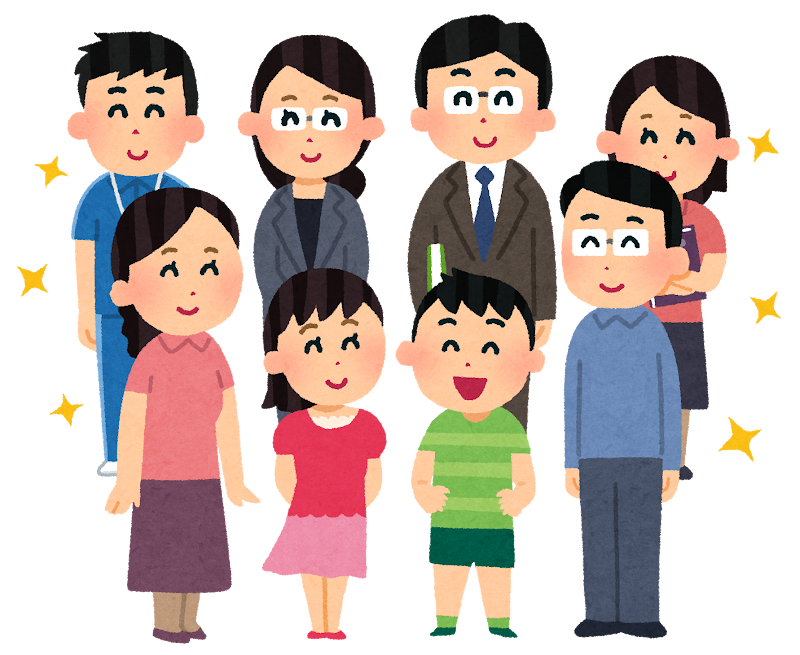
体育を見学します。とか、薬を持たせています。とかの連絡程度かなと思います。
でもこのような小さい連絡が信頼関係に繋がっていくように思います。
↑のようなことは特に低学年の子では、自分でわからないので書いておいてくださると大変助かっていました。
(見学するって書いてあるのに、体調悪い子忘れて体育に参加しかけている子とか薬飲み忘れてるとかほんとにある。)
書いておいていただけると声掛けできます(*^^*)
急に保護者さんに会っても「あの時の連絡ありがとうございます」となどと信頼関係を深めることができました。
まあ、今のご時世メールやらLINEなんかで一斉送信とかでもいいと思うのですが、
なんやかんや連絡帳が無くならない理由は上記のようなことがあるからかなあと個人的には思います。
そのうちこれもIT化していくのかもしれませんね。
(今現在そういう学校もあるのかも…?)
連絡帳の実態
【マニュアルとか研修とかない】
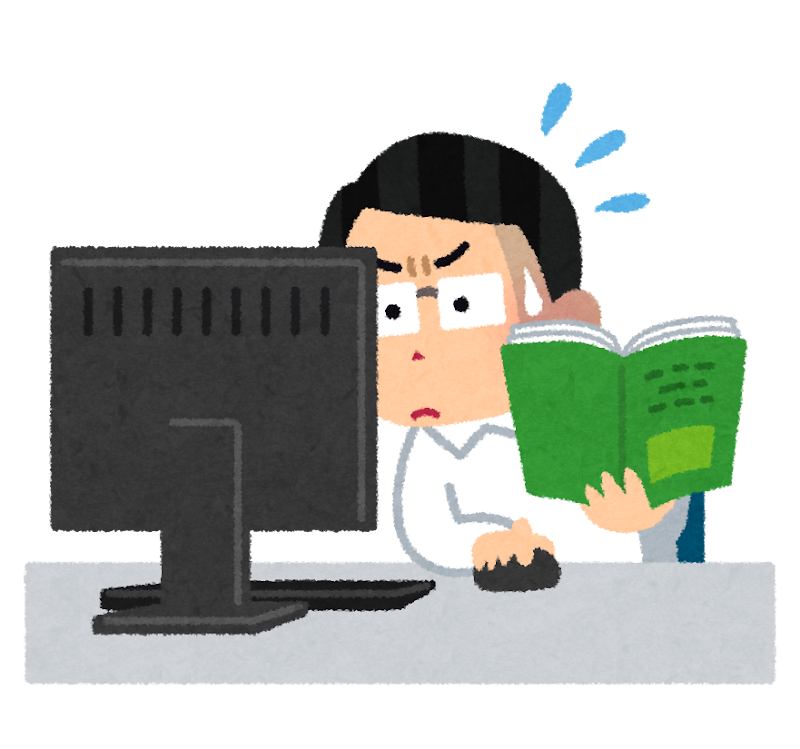
何を書かせなければならないとか
いつ書かせるとか
クレームが書かれていたらどうするとか
一切マニュアルがありません。
だからこそ、どうすればいいのかわからん。と思っていました。(笑)
お困りの先生や保護者さんのために以下連絡帳マニュアルを綴っていきます。
(※あくまでも私個人が気を付けていたことなので、あらかじめご了承ください。)
連絡帳マニュアル(まこち的)
①必ず朝にチェックしよう
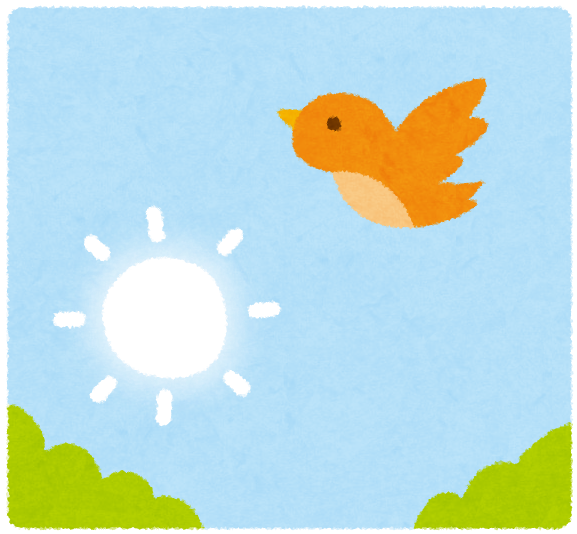
絶対に朝確認していました。
なぜなら、連絡帳確認しておらず子どもを危険にさらしてしまったら取返しのつかないことになる可能性があるからです。
例えば、一時間目に体育があり、見学をすることが書かれており、気づかず体育に参加させてしまった場合先生の確認不足です。がびーん。
子どもも「連絡帳に書いてあるから~~」と伝えてくれないこともあります。
そのため必ず朝に確認することを強くおすすめします。
めちゃくちゃ忙しいけどここは妥協してはならないと思います。
②子どもに助けてもらおう

上記でもありますが、「連絡帳に書いてあるから~」を防止するためにも
子どもたちに「連絡帳に何か書いてある人は先生に伝えてください。」とあらかじめ指導しておくとダブルチェックになります。(特に低学年)
「先生40人近くの子の連絡帳チェックしてるから、伝えてくれるとめちゃくちゃ助かるんよ!」とか言って。
子どもって思っている以上に助けてくれます。
ありがたいことにこれで確認ミスを防げたこともあります。
ありがとう当時の同胞(子ども)たちよ。
③1日が終わるまでに必ず返事をしよう。

連絡帳は子どもが毎日持ち帰ります。
保護者の方が何か書いてくださったときには、必ず返事をするようにしていました。
「連絡ありがとうござます。承知いたしました。」
が私の十八番の返しでした。
個人情報に関することや連絡帳での返信が難しい時には、
「連絡いただきありがとうございます。本日電話にて連絡をさせていただきます。」
と記入していました。
私たちも忙しいですが、保護者の方も忙しい中連絡帳に記入してくださっていることを忘れず、どんな内容であっても感謝の言葉を入れることを心がけていました。
④クレームや個人情報が書いてある時にはコピーをとろう

クレームや個人情報などについて書かれているときには、その日の連絡帳のやりとりだけでは終わらない可能性があります。
内容を覚えてるつもりでも、1日のうちにいろんなことが起こる学校生活では放課後まで正確に内容を覚えておくことは難しいです。
また連絡帳の内容を見ながら組織対応を考えることもあるので、口頭ではなくコピーを残して職員間で共通理解をすることが大切です。
⑤子どもが連絡帳に目を通すことを意識しよう
低学年であっても高学年であっても子どもは先生や親がどんな内容を書いたのかすごく気になります。
先生と親が良好な関係を築けてる場合は子どもも心地よいと思いますが、自分が怒られた(指導された)内容をが書かれていたり、クレームなどが書かれていると子どもは気になるものです。
常に子どもの目があるということを忘れてはいけません。
子どもの心の安寧が第一です。
連絡帳は残るものです。
子どものトラブルなどは電話連絡や家庭訪問をすることおすすめします。
文字で伝達するのと実際に合って話すのでは印象が大きく異なることが多いです。
文章から冷たい感じがあっても、実際に話してみるとそうでなかったりします。(先生サイドも保護者さんサイドも)
⑥感謝を書いていただいた場合にもコピーを
これは自分のモチベーションを上げるためです(笑)
学期末などに感謝の言葉を添えてくださる保護者さんがおられて嬉しい思いをした方も多いのではないでしょうか?
私は必ずコピーしてお守りにしていました(笑)
先生になって褒める機会は増えるものの、褒めてもらう機会はなかなかありません。
夜な夜なそのコピーしておいた感謝の言葉を見てやる気を出していました(笑)
最後に
いかがでしたでしょうか?
令和の時代になっても教師の仕事内容は昭和から変わっていないように思います。(いい意味でも悪い意味でも)
日々の何気ない関わりが信頼関係に繋がっていくと思います。
親が先生のことを好きなら子どもも先生のことを好きになるし、その逆もしかりです。
忙しい日々の中ですが、毎日確認する連絡帳を通じて保護者と教師の信頼関係を築けることを願っています。
最後まで読んでくださりありがとうございました。
この記事があなたのお役に立てば幸いです。
ではまた(*^^*)